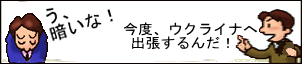
ハマっ子ノスタルジー
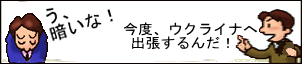
| 『ウクライナの地方都市の話』 (第2話) 広瀬裕敏 一番いい季節だった。 1982年の4月から5月、まるまる2ヶ月間、ザパロージェというドニエプロ河畔の地方都市にいた。人口は約百万人。ザパロージェッツという非力の小型車の工場がある工業都市であった。 この町に着いてすぐ、一週間ほど入院して、そこでウクライナの看護婦さんに世話になり、退院後何度かデートした。 まだ私のロシア語は拙く、いったい何を話していたのだろう。一度ドニエプロ川の遊覧船に乗った以外、ただひたすら河畔と公園を歩いていた。 ブレジネフ時代末期の何もない時代だった。ただただ新緑と川の波に散る陽光がすばらしかった。 デートの移動はたまに路面電車だった。 車も少なく、電車はいつも満員で、にもかかわらず車掌はいなかった。車内に何とかもぐりこむと、看護婦さんは粗悪な紙質の回数券を2枚バッグからとりだし、無言で近くの乗客に渡した。それが満員の車内で何人かの人の手を経由して、パンチング機まで届き、見知らぬ人がパンチしてまた同じ手を経由して戻ってくるのであった。 無賃乗車でも咎められるわけでもないのに、誰もがその作業を繰り返していた。 看護婦さんと、その先輩の看護婦さんと三人で公園を歩いていたとき、12歳前後の男の子たちが水のみ場で水を噴水のように飛ばして遊んでいる場面にでくわした。 「僕らいくつなの」 先輩の看護婦さんが子供たちを叱り付けた。当たり前のように見ず知らずの子供を叱り、当たり前のように大人の言うことを聞く子供に感動していた。 クワスの自動販売機があった。看護婦さんがおごってくれた。紙コップもなく、使いまわしのプラスチックのコップで順番に飲んだ。 あのときのウクライナは陽光にあふれ、暖かかった。 |
| 【掲載作品一覧】 |