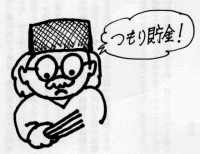 |
ハマっ子ノスタルジー
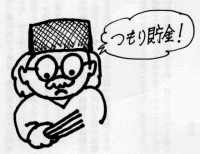 |
| 『将来の夢』 (第20話) 広瀬裕敏 私はあまり意志が強いほうではない。 目標を定めて、それに向かって邁進するなどといくことは、できたためしがない。状況に流されて馬齢を重ねてきた。 小学生のときの夢は何だっただろう。 コーラ工場の二階に住んでいたから、庭付きの家に住みたかった。山手の丘に住みたいという気持ちもあった。 中学生になってサッカーを始めて、代表クラスのサッカー選手を夢見たこともあった。(もちろん能力からいって無理なことはわかっていたけれど) 映画が好きになって、映画監督を夢見たこともある。ロマンポルノの監督でもよいと思った。 そのうち小説家にあこがれるようになった。「ロシア語学科」なるところを大学で選んでしまったのも、文学に対する漠たる憧憬があったからである。小説家であるために、病弱で奇矯でなければならないと思ったりした。精神診断テストで正常という結果がでて、むしろがっかりした。 「おまえ、高校の文集で、将来の夢何て書いたか覚えているか」 「いや何だったけ」 「高等遊民だぞ。あれは異彩を放っていた」 「そうか。そうだったかなあ」 気恥ずかしさよりも、なんだか十七歳の自分を誉めてやりたい気持ちだった。十七歳の文学少年としては、将来の成功像など恥しくて書けるかという気持ちだったのだろう。 中学生のとき、学校の帰りに友人二人と横須賀線のボックス席に座っていた。 前に座っていたヒゲのおじいさんが、しげしげと私の顔を見て、突然話しかけてきた。 「きみ、ツモリチョキンをしたほうがいいよ」 「はあー」(語尾あがる) 「実は私は人相見なのだがね。今日はタダで見てあげるから。きみは浪費のヘキがある。将来何かしたつもりで貯金する。キャバレー行きたくなったら行ったつもりでそのお金を貯金する」 「はあー」(語尾さがる) 事実であった。 確かにお金は貯まっていないが、後悔はない。何かしたつもりで何もしないで、何の意味があるのだ。何かして痛い目にあうほうがよっぽどいいだろう。 ちなみに、そのとき隣に座っていた友人は、ムコ養子の相がでている、と言われたが、これはあたっていない。 |
| 【掲載作品一覧】 |