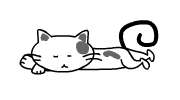 |
ハマっ子ノスタルジー
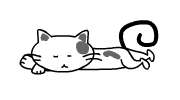 |
| 『夏休み』 (第28話) 広瀬裕敏 小学生のときの夏休み中、清涼飲料水製造業の実家はカキイレドキである。 アメリカ製のビン洗浄機の、一列ずつビンが動くガチャンという音を終日途切れることなく聞くことができる。 夏休み中に一回ていど、暑い調合室で色素や砂糖などの原料配合を間違えたのだろう、数十ケース単位で不良品がでることがあった。それらは売れないだけで害になるものではなく、従業員や社長の息子が自由に飲むことができた。母は一応息子の健康を心配して、一日3本といったふうに制限した。当時のジュースはたった3本でも舌がまっ黄色になった。 遅くとも6時を過ぎると工場の騒音がぴたりと止まる。街を行きかう物売りの音が、工場の二階の自宅からもよく聞こえるようになる。豆腐屋のチャルメラは毎日のように聞こえた。 夜が更け子供が風呂に入る時間には、風呂場の窓を通して、隣の料亭から三味線の音色や芸者さんの嬌声が聴こえてくる。 まだ港から家まで大きな建物もなく、山下公園の花火大会は家の物干し台から遠望することができた。 花街の各々の店先はきれいに掃き清められ打ち水がされていた。料亭の勝手口からラジオの野球放送が流れ、路地で板前さんが子供に線香花火を与えて遊ばせていた。 大通りを渡った近くの商店街では、一と七のつく日に地蔵尊の周りに縁日が開かれ数十軒の屋台がでた。アセチレンガスの灯り、金魚すくい、セルロイドのお面、 ヨーヨー、綿菓子、お好み焼き。 それらすべてが夏の夜の日常の風景だった。 あの頃、大人たちはよく働き、子供たちはよく遊んでいた。実家の工場は週6日、土曜の5時まで動いていた。一方私は、6年生で東京の予備校に日曜日に通うまで、習い事は3年生のときのそろばんだけだった。有り余る時間を家とその周辺の花街で遊んでいた。 夏休みに市電で単独行動を許されたのは、せいぜい根岸の市民プールくらいだったろうか。物心ついたときには家に居た、私より年上の三毛猫の行動範囲と似たりよったりだったろう。 そういえば、彼女にとっては毎年夏は迷惑なものだったろう。いたずら盛りのヒマな子供は、昼寝をしている猫を見ると、ヒゲを引っ張ったり鼻をつまんだりするのである。尻尾の上げ下げで彼女は苛立ちを示すが、最後には頭にきて、私をひっかいて 二階のまどから工場の屋根伝いに逃げていく。 私の存在を除いては、猫にとっても、住みよい家、住みよい街、住みよい時代だったに違いない。 |
| 【掲載作品一覧】 |