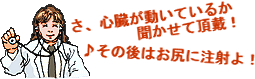
ハマっ子ノスタルジー
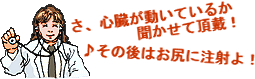
| 『ウクライナの病室』 (第6話) 広瀬裕敏 「ここは工業都市だから、次の世界大戦が始まったら、真っ先に核ミサイルの標的になるんだ。」 ウクライナの病院で同室だった高校生の発言である。 1982年の春。もう冷戦もおおかた勝負がついた時代だった。 モスクワから列車でザパロージェに着き、先発の日本人の歓迎を受けて、ホテルのベッドに入って明け方吐血した。飲みすぎと過労である。 救急車を呼んでもらって、近くの病院で検査を受け、たぶん空きベッドの都合なのだろう、別の病院に入院した。 病室は6人部屋。私以外、4人が老人で、隣のベッドが風邪をこじらせた16歳の高校生だった。 一日目は点滴につながれベッドでまるくなっていた。食事も誰かが運んでくれた。うすい野菜スープと乾燥したパン。ほとんど手をつけずにいると、若い看護婦がいったい何だったら食べるんだと、病室に飛び込んできて、私を見下ろして難詰した。 二日目はすでに回復して、動き回ることができた。自然に退院間近の高校生が私の世話係りになった。軽症者の病棟だったのだろう、毎回彼に誘われて、食事は食堂でとった。朝はミルク粥、昼は塩気のないスープ、夜は骨の多いサカナがメインだった。 一日に一回治療室に呼び出され、看護婦に尻を出すように指示され、太い注射をダーツのようにうたれた。まだエイズという言葉もないときである。 担当の看護婦は、30歳前後の巻き髪のベテラン看護婦と、私を難詰した21歳の栗色の髪のコンビだった。 一度二人に治療室に呼び出され、二回目の注射かと思ったら、日本の歌を歌えといわれた。「荒城の月」を歌った。それしか思い出せなかった。 もちろん重症者がいなかったこともあるだろうが、それにしても病室は陽だまりのように暖かかった。一千万人近く死んだウクライナ戦線の生き残りの老人たちと、無垢な高校生のせいである。 外国人だからということで、個室に移ることが検討されたとき、若い看護婦はもう一度病室に飛び込んできた。個室に移りたいのか否か、彼女の剣幕に、6人部屋に残る希望を明言した。彼女は当然だというふうにうなずいて出て行った。 6人部屋に残りたかった理由は、担当の彼女だけではなかった。いつもニコニコしている4人の老人と、私の世話を任務と感じている高校生と離れたくなかった。 一週間が過ぎて、高校生に退院許可がおりた。人は本当に嬉しいとき、文字通り躍り上がるのを知った。まだ16歳である。 次の日、私にも退院許可がおりた。身の回りを整理して退院を待つ間に、高校生のベッドに30歳前後の働き盛りの男が来た。 彼は隣の私に不安をまくしたてた。自動車工場で突然倒れたこと。こんなことは初めてだと。小さい子供が二人いること。 「心配ないですよ。」 私は入院生活の先輩面していった。でもいい加減なことではない。ここで、たった一週間で、たくさんのものをもらった。粗食さえも健康を与えてくれた。 「これ使ってください。」 ウェットテイッシュを渡し、それで初めて私が外国人だとわかったようだった。 看護婦に言われ、高校生は私の退院手続きを助けに来た。入院費はすべて無料である。 退院後、高校生とも何度か会った。冒頭のセリフは唯一今でも覚えている彼の言葉である。 帰国後何年かたって、彼の手紙で、彼が医学部に進んだことを知った。 |
| 【掲載作品一覧】 |