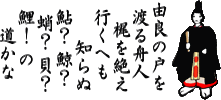
平成東京物語(その1)
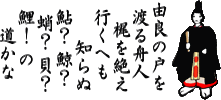
複数のライターが交互に数行ずつ綴る実験的リレー・ストーリー
行き着く先は誰も知らない・・・(舞台裏集音マイク)
| 東京駅前の信号で立ち止まる。 信号が青にかわり、動き出す人の波を見ていると、ふと微笑みたくなることがある。夕暮れだからだろうか、無表情の集合体が逆にとても人間くさく思えるからである。 (鯨)2005.09.25 都心では、この時刻に道を歩いて夕陽を正面から浴びる場所は、数少ない。東京駅前がそうであることに何だか不思議な気がした。翳りつつもなお透き通るような秋の夕陽に照らされると、空を見上げることを忘れた雑踏の人々も、新しい景観を誇る新丸ビルさえも、どこかなつかしげな余情を帯びてしまう。 (蛸)2005.09.26 特に今年の夏は暑かったから、涼しい風が心地よい。私がこのあたりで働いていた頃にはなかった高いビルが次々と出現していて圧倒される。でもこれから会うのは古い友人。久しぶりなのでお互いわかるかどうか心配。メールでは顔も見えないし、声も聞けないから。 (鮎)2005.09.26 何年ぶりだろうか。かれこれ二十年にもなる。屋台を引っ張っていた辛い日々が蘇る。うだるような夏の暑さと身体の芯まで凍える冬の寒さ。若かったから耐えることができたのだろう。今日のように穏やかな日の記憶はほとんどない。夕暮れの美しさに目を留めることもなかった。 (貝)2005.9.27 20年前苦学生だった。二浪の後美大に通っていた。 ひょんなことで知り合いになったジイサンの手伝いで東京駅前でラーメンを作っていた。車があればよいのに、ジイサンは月島から屋台をひっぱていた。寄る年波で帰りの永代橋を渡るのがしんどくなったのだろう、近くの3畳間に住んでいた貧乏学生に声をかけたのである。 今日、まさに屋台があったところで待ち合わせているのは、そのとき知り合ったOLである。彼女は死んだジイサンの住所を知っていたらしく、半年前年賀状を出していた。たまたま何年ぶりかで線香をあげに行った私が、ジイサンの奥さんから見せてもらい、連絡を取り始めた。 (鯨)2005.9.27 彼女が初めて我々のラーメン屋へ来たのは冬の寒い夜だった。まだ新入社員だった彼女は残業の後、どうにもお腹がすいて駆け込んできたという感じだった。それまで寒くて早く切り上げたいとジイサンの顔をチラチラ見ていた私は、急に元気づいて「いらっしゃい」と声を出したのをおぼえている。 (鮎)2005.9.28 それからのことは、若さとは残酷なものだと物知り顔で語れるほど私の中で風化しておらず、今も悔恨の痛みなしには振り返ることができない。 しかし、20年ぶりの彼女は、そのような思い出から遠くかけ離れた姿で現れた。相手から声をかけられるまで、その女性がまさか彼女だとは思えなかった。 (蛸)2005.9.29 「平山さんですね、小川です。」 二十年でこれほど変わるものだろうか。私は驚きの表情を隠せぬまま、深緑色の着物姿の相手の顔を見つめた。初老に差し掛かったともいうべき皺の多い顔のところどころに確かにあの娘の面影が潜んでいるように見えた。 「今日は娘が急用でどうしても来られなくなりました。そこで、母親の私が代わりに参りました。実は、この絵にサインをしていただくようにと娘から頼まれましたものですから・・・」 暗色の小さな風呂敷包みから現れたのは、二十年前に私が四号カンバスに描いてあげたあの娘の肖像画であった。 (貝)2005.9.30 あの頃いい絵の具も買えなかった。色あせが目立つ小さい絵を見つめた。 画学生が描いたと一目で判るまじめな絵だった。タッチが今とは全然違う。いや、まだ自分のスタイル自体持ってない習作だった。ただモデルに対する愛情はすぐわかる。美しく描きたい、その一念がひとつひとつのデイテールからあふれ出ていた。さらによく観れば、作者の鬱屈した飢餓感がすぐに見透かされることだろう。 あの時代の自分を直視させられたようで、眼を背けたくなる気持ちと裏腹に、駅前の雑踏の中でじっと小さい絵を見続けた。 (鯨)2005.9.30 「平山さんのことは、娘の夏子からよく聞かされていましたので、すぐにわかりました。ひげが昔のままならわかるはずだと言われたのです。」 母親から話しかけられ、我に返る。一体彼女は私のことを何と話していたのだろうか。 (鮎)2005.9.30 そんなことを思いながら、請われるままに絵の隅にフェルトペンでサインを入れ、ちょっと考えてから、今日の日付を加えた。母親は絵を受け取ると、とても嬉しそうな顔をして大切そうに風呂敷に包んだ。 「娘からは後日、今日の失礼をお詫びする連絡が入ることと思います。本当にありがとうございました。」 母親は最初に会ったときよりも幾分華やいだ様子で深々とお辞儀するとその場から立ち去った。 (貝)2005.10.1 「夏子、見てきたよ、昔、おまえをふった人」 後で知ったことだが、母親は帰るなりそう言ったらしい。 「ふられたわけじゃないって何度言ったらわかるの。だから行かせるの、いやだったんだ。何か変なこと言わなかったでしょうね」 「言うもんかね。絵にサインしてもらっただけさ。でも、あの人、おまえの絵を見て涙ぐんでたよ」 「あの人が? ウソでしょ」 「ホント。見て見ぬふりをしてあげたけど」 (蛸)2005.10.01. 夏子の母親とはほとんど話をせずに別れた。 夏子には、何故突然別れなければならなかったのか、何故行き先も告げず日本を離れたのか、順を追って話をするつもりでいた。 何回かのメールで説明しきれる話ではなかった。ソ連が崩壊し15年たった今、ようやく話せる事情だった。 (鯨)2005.10.3 昔、ジイサンは事業に失敗して、巨額の借金を背負っていた。それを清算するのに私が一肌脱いだのだった。命懸けと言った方がいい。 1985年、当時のソ連邦レニングラード市にあるエルミタージュ美術館で見物人のひとりが硫酸とナイフでレンブラントの名作「ダナエ」をひどく傷つけるという事件が起こり、日本でも話題になったことがある。実は、あれは金に困っていたソ連が日本のある絵画収集家に法外な値段で売り付けるために打った二十世紀最大の猿芝居なのだった。予めすり替えられたレプリカに傷をつけ、本物はコンテナ船でこっそり日本へ持ち込まれた。仲介したのはKGBと日本のその筋の組織。ナホトカ港で受け渡しの際の鑑定人として私に白羽の矢が立った。引き受ければジイサンの借金は帳消しにされ、その上、まとまった金まで入るという好条件だった。 (貝)2005.10.03 私が仕事の依頼を受けたのは1985年の7月だが、その年の2月、日本では闇将軍と呼ばれた元首相が緊急入院し、その政治力が致命的に揺らいでいた。ソ連では3月、前書記長の死去を受けミハイル・ゴルバチョフが新たなリーダーになったものの、その権力は盤石ではなかった。両国の権力機構の各部に隠微な空白が生じていた。私が引き受けた仕事に対して、日本とソ連は、当局のある部隊は支援を与え、別の部署は黙認し、他の機関はスキャンダルを阻止すべく追跡を開始した。誰が味方で誰か敵かわからぬきわめてきわどい状況に私は置かれた。 もちろん当時の私には、そのような複雑な事情はわからなかった。しかし、私の相棒となる人が言った次の一言によって、私は仕事の危険さを知った。 「黙って姿を消しなさい。大切な人がいる場合は、なおさらです」 (蛸)2005.10.04. 私は唖然とした。そのころの私にとって大切な人と言えば夏子しかいなかったが、彼女の前から姿を消さなければならないような仕事を引き受けてしまったとは考えていなかった。知り合ってからの半年、彼女のいない人生なんて考えたことがないほど彼女に夢中だった。 しかしジイサンにもジイサンの奥さんにも世話になっていた私は、今さら依頼を断るという状況ではなかった。 (鮎)2005.10.5 「きのうは会えなくて残念だった。お母さん、よく似てるね。浦島太郎になったのかと思った。病気がちだと聞いたけど大丈夫かな。お見舞いに行ってもいいのかな。」 メールを書き進めているうちに、彼女はまだ私を完全には許していないことに気がついた。あの絵にサインを求めたのは、20年前の日々はもう封印された思い出だということを、私に悟らしめるためだったのだ。でも私は浦島太郎だった。忘れることはできない。忘れたくない。会って話すつもりだった、彼女と会うまでの約20年、彼女と別れてからの20年を説明しようと思った。 「自分のことを勝手に話します。」 (鯨)2005.10.6 パソコンに向かってわが半生を書き綴りながら、いつも念頭から離れないことがあった。レンブラントの名画をめぐって行動を共にしたナターシャのことは書くべきだろうか。私はパソコンから目を離し、窓の向こうの夜空を見上げた。 (蛸)2005.10.06. レンブラント作品の鑑定が仕事だと聞いて、私の心が躍った。私が油絵を志すようになったのは、元々レンブラントの影響だったからだ。日本に来た彼の絵はもちろんすべて見ていた。 今は鑑定人として多少名が知られるようになったが、そのころは単に画家の卵であったわけだから、絵を描く以外の勉強をしなければならなかった。 レンブラントの絵を見に、ヨーロッパの美術館を回り、旅の最後にレニングラードのエルミタージュ美術館へ行ったときに初めてナターシャに会ったのだった。 (鮎)2005.10.7 あられもない姿で横たわる豊満な肉体をもてあますダナエに圧倒されながら、まもなくこの絵が日本人収集家によって独り占めされ、その後、ここを訪れる人々は、修復されたことになっている贋作を鑑賞することになるのかと思うと、ジイサンのため、自らの生活のためとはいえ、心が痛まないわけはなかった。この絵をナホトカ港の倉庫で確認するのが私に課せられた役割であった。念のため、頬の辺りの乾燥した絵の具に入ったひび割れた様子を詳細に見つめた。ダナエは私の瞳に焼き付き、心には罪悪感のおりが積もった。 そんな私の前にナターシャは現れた。均整の取れた体つき、しなやかな身のこなし、顔をつんと上げ、お尻を軽く左右に振って、ダナエと私の間を横切ってから、考え直したように、私の方へくるりと向きを変えると、澄んだ黒目がちのつぶらな瞳で私を見据えながら、足元まで寄ってきて、革靴に身体を押しつけたまま丸まった。ビロードのような黒い毛皮がつやつやと輝くペルシャ猫で、首に胡桃大の鈴が上品なピンク色のリボンで結わえてあった。美術館の人に聞くと、半年ほど前からここに住みついている捨て猫で、最近、亡くなった倉庫係がナターシャと名付けて可愛がっていたという。何を思ったか、ナターシャは私のそばから離れようとせず、とうとうホテルまでくっついてきた。 (貝)2005.10.7 なぜ猫のことなど思い出したのだろう。 この20年間まったく女がいなかったわけではない。ただ今考えるに、本当に愛した女(とメス)は夏子とナターシャだけだった。 ナターシャのしなやかな肢体を見て夏子を想像するのは不謹慎だったであろうか。そして気が向かぬと帰ってこないナターシャを待つとき、夏子の心情が痛いほど感じられた。連絡をとりたい。ナターシャの美しい毛並みをなでながら何度も思った。 気を取り直してパソコンに向かった。 「僕が新潟生まれで、東京に出てきて浪人した後、美大に通っていたことは、もちろん知っていたよね。」 (鯨)2005.10.7 夜明けが近づいていた。もうすぐ東京に陽が昇る。 夜もすがらキーボードを叩き続けた指が勝手に動き、 「夏子、君は僕の人生の夜明けだった」 と、恥ずかしいような文章を打ち出した。しかし、実際そうだったのだ。私は夜明けを見ずに育った。新潟には、海に沈む夕陽はあるが、地平から昇る朝日がない。私の人生も似たようなものだった。レンブラントが描くどこか物憂げな光の陰影に惹かれたのは、そういうことも影響しているのだろう。そこに一条のまぶしい光が射した。何の屈託もない光を浴びたのは初めてだった。私は夜明けの太陽を夏子に見た。 (蛸)2005.10.08. その頃、夏子は本物のダナエが飾ってある自分の寝室のベッドでワインを飲んでいた。カーテンの隙間から朝日が射し込んできたので、夜が明けたことを知った。平山からの二十年ぶりの連絡があった日から、どうにも気になって眠れない夜が続いている。調子がおかしいので母親に頼んで代わりに会いに行ってもらったのだが、あの日を境にして、何だか調子が戻ってきたような感じがした。それだけではない。眠れない日は続いているのに、身体の芯から力が漲ってくるようなのだ。平山がサインした若い頃の自分の肖像画はクローゼットの隅に風呂敷に包まれたまま置いてあった。ワインも三杯目でようやく少し効いてきたようだ。夏子はそのまま眠ることにした。 (貝)2005.10.8 麻布の高層マンションから見える東京の朝日は早い。けれでも月島でみたいに朝の喧騒を味わうことはできない。新聞配達の自転車の音。お年寄りたちの朝のあいさつ。あのころその中で自分の才能に不安を感じながら布団にくるまっていた。 「新潟の家族は、母親と妹だけで、父親は死んだと言ったと思うけど、実は父親は失踪したんだ。出稼ぎに行ってそのまま帰らず、というやつ。 したがって家は貧しかった。何とか絵描きになりたくて東京に出てきたけど、アルバイトの連続だった。」 (鯨)2005.10.10 ここまで書いて、私はコニャックを啜った。二十年前、ジイサンと知り合い、窮状を放っておけなくなって、屋台を手伝ったが、あまり助けにはならなかった。そこへ夏子が現れ、親しくなったのも束の間、思いもよらない話が舞い込んだ。甘ったるいアルメニア産のコニャックの味を教えてくれたのは、夏子だった。 (貝)2005.10.10 知り合った頃の夏子は若いのに酒に詳しかった。貧乏学生だった私はそれまで安いお酒しか知らなかったが、夏子は色々なワイン、コニャック、ブランデーの味を私に教えてくれた。心地よい酔いは私を饒舌にし、夏子相手に絵描きになる夢や自分のレンブラントの絵に対する想いなど延々と語ったのである。 (鮎)2005.10.11 夜が明けても夏子へのメールづくりは終わらなかった。 しかし、久しぶりの徹夜はさすがに疲れた。私はパソコンから離れ、壁にかかった「ダナエ」を見た。夏子と会えなくなってからの20年間、この絵だけが私を支えてくれた。 私の知るかぎり、この世には三つの「ダナエ」がある。ひとつはエルミタージュ美術館、もうひとつは私の部屋、残りのひとつの行方は私も知らない。ソ連崩壊から15年たち、事件の真相と、どれが本物であるかを知る者は、ついに私一人になった。長い空白の理由を夏子に話すことができるようになったのである。だが、そのことだけは、メールではなく直接伝えなければならないと私は思った。 (蛸)2005.10.11. 「絵描きの卵らしく、路上で似顔絵描きもよくやりました。ただ面白くもなんとも無かった。またうける絵も描けなかった。暗い絵だってレンブラントクラスなら感動を呼ぶけど、あの頃の僕の絵は、何と言うか、浅薄な暗さだった。丸の内口のジイサンの屋台の脇で描いたあなたの絵は会心の作でした。初めて描きたい絵が描けたと思ったんです。明るく聡明な貴女を物憂げに描いたけど、貴女も喜んでくれましたね。」 (鯨)2005.10.13 今考えると描いている時間は至福のひとときだった。朝からワクワクして夏子に会える夕方が待ちきれなかった。絵を描いているのだから彼女を思う存分見つめることも出来たし、通行人も立ち止まる中、少し恥ずかしげにしている夏子がたまらなくかわいらしかった。 (鮎)2005.10.14 レンブラントは、最愛の妻サスキアを失って「ダナエ」を描いた。 私は夏子を失ってその「ダナエ」を得た。しかし、この「ダナエ」は、謀略で汚れている。浅慮によって謀略の中に身を置いてしまった私にふさわしい「ダナエ」であった。 私にとって真に価値あるものは、そのような「ダナエ」ではなく、 20年前に描いた夏子の肖像であっのだと今はっきりわかる。 (蛸)2005.10.14. 朝日はだいぶ高く昇り、白く輝き出し、徹夜明けの目には眩しい。まだすべてを語り尽くしたわけではなかったが、無性に夏子と言葉を交わしたくなった。「お早う」の一言だけでよかった。だが、夏子はまさかこんな時間に起きてはいないだろう。それならそれでいい。思い切ってパソコンから夏子の携帯にメールを送ってみた。 「お早う、夏子、君のパソコンアドレスを教えてください。平山」 五分が過ぎても応答はない。やはり、起きてはいなかったようだ。あきらめかけたその時、着信を示す警告音が頼りなさそうに鳴った。 (貝)2005.10.14 夏子からだった。 「昨日はごめんなさい。体の調子が悪かったのは本当だけど、実はまだ会う勇気がなかったの。あなたの書いた絵を見ているうちに朝になってしまいました。私のパソコンメール次の通りです。」 行間にあふれる夏子の感情が充分感じられた。 「夏子様。 携帯メールでは言い尽くせないこと話します。 貴女の絵を描いた晩、月島に帰ったらやくざの借金取りがジイサンを待っていました。商売道具の屋台を壊すことはなっかたけど、かなりどんぶりは割られました。ジイサンの息子さんに街金の高利の借金がかなりあることを知りました。ジイサンはやる気をなくして次の日から屋台をひっぱることをやめました。ラーメン売ってるだけでは返せる額ではなかったのです。 私は前から誘われている儲け話に返事をしました。」 (鯨)2005.10.17 「そしてそのために貴女の前から姿を消すことになりました。 絵を描き上げた時には、またいつものように次の日の夕方に会えると思っていたから、お互い特別な言葉も交わさなかった。あれが最後と知っていたら、もっと貴女に言いたいことや貴女とやりたいこともあったのに。何度もあの夜のことを思い出していました。」 (鮎)2005.10.17 「それから私はレニングラードへ飛んだのです。美術館である巨匠の作品を観るためでした。その後、ナホトカへ移動し、頼まれた仕事を無事終えたまではよかったのでしたが、そこである事件に巻き込まれてしまいました。ホテルの私の部屋に刑事が捜査令状を持って現れました。レニングラードの美術館で私になついた黒猫をナホトカまで連れてきていたのですが、その猫の首に下がっていた鈴の中から、大粒のダイヤモンドが出てきたのです。それは美術館から盗まれた展示品らしいのです。もちろん、私には身に覚えのないことでした。美術館の倉庫係の仕業のようでしたが、本人はすでに死亡していたため、私にまで容疑が掛けられました。無実を主張したものの、ソ連邦時代の裁判所では、判決が最初から決められているのも同然でした。私は共犯とみなされ、国家財産横領の罪により三年間の服役を言い渡されたのでした。」 (貝)2005.10.18 当時を思いだすときのいつもの癖だが、私はまるで苦いものを飲みこんだような表情になる。折しも、テレビが不愉快なドキュメンタリーを流していた。アジアの某国の外交官が豪州にニセ札を大量に持ち込もうとして摘発された事件を扱った番組であった。 あの程度の国家でも、ニセ札製造を国家事業としておこなえば、本物と見分けがつかぬほど精巧なドル紙幣をつくることができる。しかし、そのニセ札でさえ、レンブラントの贋作を作ることに比べれば児戯に等しい。 思えば、ソ連とは不思議な国であった。宇宙開発をはじめとする先端的な科学技術で米国と冷戦を戦う一方で、19世紀の古い伝統を体制の中に残していた。マニアックな手作業の職人たちも温存されていた。たとえば、革命の父レーニンの遺体を、ありし日のままの姿で保存するなどという奇怪な処置は、先端技術と19世紀的職人芸の結合なしには不可能である。本物そっくりの「ダナエ」の制作は、ソ連という国の、この体質的な能力なしにはなしえなかったであろう。 ゴルバチョフの新政権が、旧政権下で立案された「ダナエ計画」を知ったのは、エルミタージュ美術館で「ダナエ」を傷つける事件が発生した直後であった。傷ついた「ダナエ」が贋作であること、本物は国外に流れる寸前であることを知った新政権は驚愕した。贋作がもう一枚存在するという情報もこのときもたらされた。KGBが二枚の贋作を作ったのは、何をやるにも常にスペアを準備するというこの組織の伝統的な体質に根ざしている。何らかの予想外の事態が起こったとき、スペアがあれば、それをどう使うかはそのとき次第としても、いずれにせよ即座の対応が可能になるからである。 計画はすでに実施に入っていた。しかも政権移行期にあっては、KGB内部に新政権の指揮がまだ貫徹していなかった。そこで、次のような緊急指令がKGBに、そして全国の治安・警察組織に向けて発せられた。 1.レンブラントの名作「ダナエ」の国外流出を阻止せよ。 2.本指令でいう「ダナエ」とは本物を意味し、贋作については、もしそれが上記任務遂行のために必要ならば、国外流出を黙認してもよい。 ソ連特有の言い回しのこの文書が意味することろは、本物をエルミタージュ美術館に戻せば「ダナエ」計画の立案者や実行者たちのことは不問に付してもよいということであり、さらに事ここに至って「ダナエ」取り引きを中止できないのなら、その場合は贋作を売れと示唆したのである。新政権としては計画そのものの中止をめざしつつも、その方針に服さない部署や部隊があることを想定し、計画がそのまま進行した場合にそなえて、贋作を売らせることで事態を収拾しようという二段構えの方針であった。 そのころ、本物の「ダナエ」は、贋作のスペアとともに、ソ連極東の港町ナホトカにあった。そのとき私もナホトカにいた。そして私の逮捕は、ダイヤモンドの密売に名を借りてはいるものの、その実、「ダナエ」計画の収拾に私を利用しようというソ連側の(といっても、そのとき彼らは一枚岩ではなかったので「その一派の」と言うべきか)策略であったのだ。「裁判」なるものが逮捕の翌日おこなわれ、翌々日に判決が出たということがそれを雄弁に物語っている。しかし、そのような背景や動きなどは、当時の私には理解の外にあることだった。 (蛸)2005.10.18. 「取調べ室に日本語のうまい男が現れ、しばらくここに泊まってもらうといいました。僕は的外れに、ナターシャはどうなったかとききました。男は苦笑いして、心配ないとひとこといってでていきました。その後何の取調べも無く、留置場に4日間留め置かれました。いつ拷問されるかと心配しましたが、何も無く4日目の朝に釈放され、強制退去を命じられました。 後から考えると、多分その間にKGBのスイスあたりの口座に振込みが確認され、本部から指示があったのでしょう。 あなたがわが国でやったこと、ここで逮捕されたことは、日本に帰っても何も話さないように。男は凍りつくような目つきで僕に宣告しました。 僕はまた、愛する猫に何も告げることができずに、そのまま横浜航路の船に載せられました。 日本に帰って、しばらく新潟にいたのですが、背中に明らかに監視の眼を感じて、また日本を飛び出したのです。」 (鯨)2005.10.20 平山は半ばやけくそで適当に行き先を決めようと成田空港へ向かった。そして、選んだ先はフィリピンのマニラであった。日本は夏が終わったのに、空港ロビーから一歩外に出ると、全身から汗が噴き出してきた。見知らぬ土地で少々不安ではあったが、始終見張られている日本から解放されたと思うと、寧ろ喜びの方が強かった。中心街でホテルでも探そうと歩き始めたら、恐ろしく古ぼけた日本車に乗った若い白人が私に声を掛けてきた。 「事務所まで戻るんだが、乗らないか?」 屈託のない笑顔に訛りの強い英語で話しかけられると、平山の警戒心は緩み、つい助手席に乗り込んでしまった。 「ウラジーミル・シェンバリドだ。バロージャと呼んでくれ。」 ハンドルを握りながら片手を差し出してきたので、平山は心に引っかかるものを感じながら握手した。 「ロシア人かい?」 「その通りだよ。」 「ここで何をしているんだ?」 「ソ連漁船が極東で獲った冷凍イワシをここの工場へ運び入れて、缶詰にして売っている。・・・というのは表向きの話で、実は、KGBのマニラ支局長兼任だ。たった一人しかいないがね。」 これを聞いた平山は一瞬怪訝そうな表情をしたが、次の瞬間には、大声で笑い始めた。涙さえ出てきた。この様子を見ていたバロージャもつられて笑った。 (貝)2005.10.21 今は、夏子には、こんな風に説明するしかなかった。実際、留置場に4日間いたことも、強制退去させられたことも、その後フィリピンに行ったことも、すべて本当のことである。しかし、メールでは書けないことがあった。 留置場で「ダナエ」の贋作を見せられたときは、心臓が止まるほど驚いた。私はそれが贋作であるとはすぐには見抜けなかった。「ダナエ」は日本の買い手に渡り、今日明日中にも船に積みこまれるはずなのだが、それが戻ってきたのかと思った。それほど本物そっくりだったのだ。その「ダナエ」を指さしながら、 「3年の服役を逃れる道がひとつだけある」 彼らはそう言って、ある任務に私をつかせようとした。 私は事態が飲み込めていないから、あんなことが言えたのだろう。エルミタージュ美術館で切り裂かれた「ダナエ」が欲しい、と、まるで交換条件のように、私は彼らに言ったのだ。私の願いは、驚くほどスンナリ認められた。あっちの贋作は今ではメチャクチャに傷ついており、私が本物を戻す手伝いをするのなら、あんなものはくれてやってもかまわないと彼らは考えたのかもしれない。 こうして、私が留置場にいる間に、傷ついた「ダナエ」がナホトカに到着した。これで3枚の「ダナエ」すべてがナホトカに集まったことになる。そして、最終的には、そのうち1枚がソ連にとどまり、1枚は日本の買い手が持ち去り、残りの1枚は私のものになった。 (蛸)2005.10.21. そのころ日本でアンケートを取ると、一番恐れる国として最初に挙がるのがソ連であった。スターリンの独裁、KGB、得体の知れない社会システム、情報が少なかったから尚更近づきがたい印象であった。今3年の服役と言われていても、3年後に釈放される保障は全くなかった。このままこの北の果てに留め置かれ、夏子にもナターシャにも会えぬまま残りの人生を過ごすことになるかもしれないという恐怖に私は震えあがった。彼らの提案に乗らないという選択肢はなかった。それが彼らのいつものやり方だったのだろうが、他のことを考える余裕がなかった。 (鮎)2005.10.25 平成東京物語(その2)へ続く (舞台裏集音マイク) |